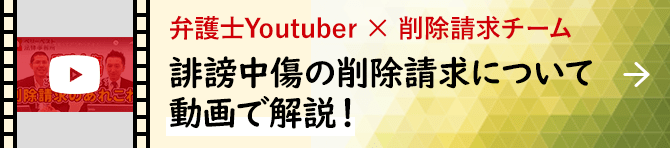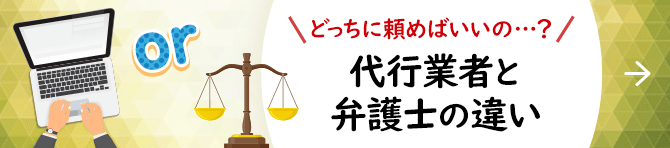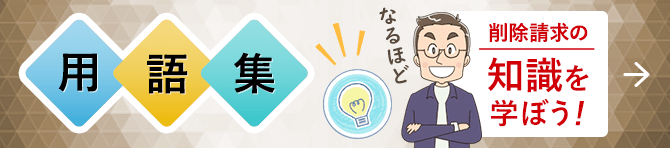開示請求・口コミ削除
SNSでの誹謗中傷、炎上、風評被害など
ネットトラブルのご相談は弁護士へ
弁護士コラム
- 削除依頼・投稿者の特定
- 全コラム一覧
- 【法人】誹謗中傷・風評被害
- ネット誹謗中傷に対する慰謝料請求|自社の信頼と損害を取り戻す方法
-
誹謗中傷・風評被害法人2025年07月23日更新

ネット誹謗中傷に対する慰謝料請求|自社の信頼と損害を取り戻す方法
インターネット上(以降「ネット上」と表記)での誹謗中傷は、企業に深刻な影響を与える可能性があります。ブランドイメージや従業員のモチベーションの低下、業績の悪化などさまざまなリスクが生じるおそれがあるため、早急に対策を講じるべきです。
ネット上の誹謗中傷被害に対する対策のひとつが、慰謝料請求です。加害者を特定し、慰謝料請求をすることで違法行為は許さないという企業の姿勢を示すことにより、自社の信頼回復や損害の補填につなげることができるでしょう。
本コラムでは、ネット上での誹謗中傷により慰謝料請求を検討している法人担当者や事業者に向けて、慰謝料の相場や慰謝料請求の手順、自社の名誉回復を実現するポイントなどについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
-
Google口コミの
ネガティブ投稿 -
SNSでの
誹謗中傷 -
口コミサイトの
ネガティブ投稿
弁護士にご相談ください
お問い合わせに費用は発生しません。
安心してご連絡ください。
1、企業のネット誹謗中傷の現状と慰謝料相場
ネット上で誹謗中傷をされた場合、企業はどのような被害を受けうるのでしょうか。以下では、企業のネット誹謗中傷の現状と慰謝料相場について説明します。
-
(1)ネット上で行われた誹謗中傷により事業者が受けうる被害
ネット上の誹謗中傷を放置すると企業にとって深刻な被害が生じるおそれがあります。
事業者が受けうる主な具体的な被害は以下のとおりです。- 名誉毀損による社会的評価やブランドイメージの低下
- 売り上げの減少や株価の低下による業績の悪化
- 従業員のモチベーションの低下による離職者の増加
- 採用活動への悪影響
ネット上での誹謗中傷は、あっという間に拡散し被害が拡大してしまうため、早急に対策を講じなければなりません。
-
(2)慰謝料請求を検討すべきケース
SNS、掲示板、ブログ、口コミサイト、投稿サイトなどのウェブ媒体は、不特定多数の人が閲覧する可能性があるものといえます。
そのような媒体に企業を誹謗中傷する内容が投稿され、それが企業の社会的評価を低下させるものであると認められる場合、名誉毀損にあたり、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります(民法709条)。
ネット上で、以下のような事実無根の投稿が確認されたときは、加害者に対する慰謝料請求を検討した方がよいでしょう。- 賞味期限切れの食材を利用している
- 国産と表示しているが実は外国産の食材を使用している
- 不正に補助金や助成金を申請している
- 食事に害虫や害獣が混入していた
- 会社の役員が反社会的勢力とのつながりがある
- 社長が不倫をしている
- 残業代を一切支払わないブラック企業だ
-
(3)慰謝料請求は難しいケース
ネット上で誹謗中傷されたとしても、以下のようなケースだと慰謝料請求は困難です。
① 加害者が特定できない
ネット上での誹謗中傷は、基本的には匿名で行われます。したがって、慰謝料請求をするためには、請求相手である加害者を特定しなければなりません。
加害者の特定には後述するような「発信者情報開示請求」という手続きが必要になりますが、誹謗中傷の投稿から時間がたちすぎていると、投稿者の特定に必要なログが削除されてしまい、投稿者の特定ができないケースがあります。
そのため、誹謗中傷に対する慰謝料請求を検討しているのであれば、早期に対応しなければなりません。
② 摘示された事実が真実であった
誹謗中傷の投稿がなされたとしても、以下の3つの要件を満たした場合、違法性が阻却されます。すべて該当すると慰謝料請求できなくなる条件
- 名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であること
- 名誉毀損行為の目的が専ら公益を図ることにあること
- 事実の真実性が証明されたこと
つまり、誹謗中傷に見える発言が、一般市民にとって生活や社会に関係する重要な問題に関係し、かつ、社会のためという目的で発言しており、さらに、事実であることが証明できた場合は、投稿者を特定できたとしても慰謝料請求は認められません。
③ 時効が成立した
誹謗中傷による慰謝料請求には、損害および加害者を知ったときから3年という時効があります。また、加害者がわからないまま期間が経過した場合でも、投稿されたときから20年を経過すると時効が成立してしまいます。
そして、時効が成立してしまうと慰謝料請求ができなくなります。 -
(4)ネット誹謗中傷の慰謝料相場
法人や事業者に対するネット上での誹謗中傷の慰謝料相場は、事業規模や被害の程度、内容によって大きく異なります。過去の判例や事例を前提に考慮すると、50~100万円程度がネット誹謗中傷の慰謝料相場になるといえるでしょう。
慰謝料額を検討し、裁判などで判断していく際の考慮要素としては、以下のような事項が挙げられます。- 被害の程度:誹謗中傷の内容、悪質性、期間、頻度など
- 被害者側の事情:知名度の大きさなど
- 加害者側の事情:動機や目的、影響力の大きさなど
2、弁護士なしで可能? 慰謝料請求の手順
企業に対するネット上での誹謗中傷があった場合、弁護士なしで慰謝料請求ができるのでしょうか。以下では、ネット上で誹謗中傷があった場合の慰謝料請求の手順について説明します。
-
(1)ネット誹謗中傷の慰謝料請求手順
ネット上で誹謗中傷の被害を受けたときは、以下のような流れで慰謝料請求を行います。
一般的な慰謝料請求とは異なり、加害者を特定するための手続きが必要になるのがネット誹謗中傷の慰謝料請求の特徴です。
① ネット誹謗中傷に関する証拠を保存する
ネット上で誹謗中傷を受けた場合、まずは誹謗中傷の投稿や書き込みの証拠を保存します。具体的な証拠収集の方法については、後述します。
② 加害者を特定するための発信者情報開示請求
ネット上での誹謗中傷は、多くのケースにおいて匿名で行われます。そのため、慰謝料請求をする前提として、加害者を特定する必要があります。そのために必要になるのが「発信者情報開示請求」です。
発信者情報開示請求は、サイト管理者に対する発信者情報開示の仮処分とプロバイダに対する発信者情報開示請求という2段階の手続きが必要になります。それぞれの詳しい内容については後述します。
③ 加害者に対して内容証明郵便を送付して慰謝料請求をする
発信者情報開示請求によって加害者を特定できたら、加害者に対して慰謝料請求を行います。
慰謝料請求は、内容証明郵便を利用して慰謝料の支払いを求める通知書を送付するのが一般的な流れです。内容証明郵便が加害者に届いたら加害者から何らかの反応があるケースがほとんどなので、加害者の回答を踏まえて交渉を進めていきましょう。
加害者が慰謝料の支払いに応じる意思を示したときは、金額、支払い方法、支払い期限などを取り決めた上で合意書などの書面を作成するようにしてください。
他方で、加害者から完全に無視をされ、何も連絡がこない場合は、内容証明郵便に記載した期日まで待ち、訴訟などを通じて内容証明に記した通りの請求を行っていくことになります。
④ 交渉で解決できないときは裁判所に訴訟を提起する
加害者が内容証明郵便を無視する、誠意ある回答をしない、というような場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。
裁判では、被害者側が誹謗中傷による権利侵害や損害を立証する必要があります。発信者情報開示請求が認められているのであれば、権利侵害の事実については一応立証されている可能性が高いでしょう。ただし、損害額などについては別途立証が必要となります。被害者・加害者双方がそれぞれの言い分を伝えたのち、裁判所はまず和解を提案するケースが多いです。和解が難しい場合は、慰謝料の支払いを命じるか否か、その金額はいくらかなどの判決が下されることになります。 -
(2)重要! 証拠収集の具体的方法
ネット上での誹謗中傷を理由に発信者情報開示請求および慰謝料請求をするためには、権利を侵害されたことを証拠により立証していかなければなりません。
ネット上での誹謗中傷の事案では、SNSや掲示板などの投稿や書き込みが証拠になりますので、以下の情報がわかるようにスクリーンショットを利用して保存するようにしてください。- 投稿された日時
- 投稿された内容
- 当該サイトのURL
なお、該当の投稿だけでなく、その前後の文脈も重要になりますので、該当投稿との連続性や投稿経緯がわかるように関連する部分はすべて保存するようにしましょう。
-
(3)慰謝料請求に必須! 発信者情報開示請求
ネット上での誹謗中傷を理由に慰謝料請求をするには、誹謗中傷の投稿をした加害者を特定しなければなりません。匿名による投稿だったとしても発信者情報開示請求という方法により投稿者を特定することが可能です。
発信者情報開示請求は、以下のようにサイト管理者に対する発信者開示請求とプロバイダに対する発信者開示請求という2段階の手続きを踏む必要があります。どちらも非常に専門的な手続きになりますので、確実に投稿者を特定するためにも専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
① サイト管理者に対して発信者情報開示請求をする|発信者情報開示の仮処分
まずは、誹謗中傷の投稿がなされたサイトの管理者に対して、投稿者のIPアドレスおよびタイムスタンプの開示請求を行います。
任意の開示請求ではこれらの情報を開示してくれることはありませんので、通常は発信者情報開示の仮処分という手続きをとります。裁判所に仮処分の申立てをすると債権者面接、双方審尋が行われます。そして、申立てが認められると担保金を供託すれば仮処分命令が発令されます。
仮処分命令が発令されればサイト管理者は、それに応じてIPアドレスやタイムスタンプの開示に応じてくれます。
② プロバイダに対して発信者情報開示請求をする|発信者情報開示請求訴訟
IPアドレスやタイムスタンプから投稿者が利用したプロバイダを割り出したら、次は、プロバイダに対して、投稿者の住所や氏名などの開示請求を行います。
サイト管理者と同様に任意の開示には応じてくれませんので、裁判所に対して発信者情報開示請求訴訟を提起する必要があります。発信者情報開示請求訴訟に勝訴すれば、投稿者の住所や氏名などの情報を開示してもらえます。
なお、現在は、法改正により、発信者情報開示命令制度が新設されました。簡単にいえば、上記①と②をひとつの手続き内で行うもので、加害者の特定まで時間的な短縮が見込めます。もっとも、発信者情報開示命令が必ずしも有益であるとは限らないため、手続きを行う際は、従来の手続きとどちらがベストなのか、事前に弁護士に相談をするのが望ましいでしょう。
3、慰謝料請求と自社の名誉回復を実現するポイント
本章では、ネット上の誹謗中傷により低下した社会的評価を回復するためのポイントを説明します。
-
(1)早急な削除と正当な請求額の設定
ネット上の誹謗中傷の投稿や書き込みを放置すると、それが拡散され権利侵害が拡大してしまいかねません。そのため、日常的に自社に対する誹謗中傷の投稿の有無をモニタリングし、誹謗中傷の投稿を発見したときは迅速に削除を行うことが重要です。
ただし、投稿者に対する慰謝料請求を予定している場合には、投稿の削除をする前に、しっかりと証拠を保全しておくようにしましょう。
また、法人や事業者に対する誹謗中傷の慰謝料相場は、事案により大きく異なりますが、50~100万円程度となるケースが多い傾向があります。相場を踏まえた適切な請求額を設定することも大切です。法外な慰謝料を請求すると企業の社会的評価を下げる可能性もあるため注意してください。 -
(2)交渉か裁判か? それぞれのメリット・デメリット
加害者に対する慰謝料請求は、加害者に直接通知書を送って交渉する方法と、裁判手続を利用する方法の2つの方法があります。
交渉と裁判は、それぞれメリット・デメリットがありますのでどちらの方法で解決するかは、メリット・デメリットを踏まえて判断しなければなりません。① 交渉のメリット・デメリット
【メリット】
・双方が合意できれば、比較的早期の解決が可能
・裁判費用がかからない
【デメリット】
・双方が合意しなければ解決できない
② 裁判のメリット・デメリット
【メリット】
・相手の合意がなくても判決により解決が可能
・相手が慰謝料を支払わない場合には強制執行が可能
【デメリット】
・解決までに時間がかかる
・裁判費用がかかる -
(3)適切な情報公開による信頼回復戦略
誹謗中傷による信頼失墜を回復するには、適切な情報公開による信頼回復戦略が重要です。
根拠のない誹謗中傷であってもそれを見た顧客や取引先などは、当該企業の商品やサービスに対して不安や不信感を抱きます。そのような不安などを払しょくするには、適切なタイミングでプレスリリースを発して、事実無根の投稿であることを伝えることをおすすめします。
また、同時に発信者情報開示請求や慰謝料請求などの法的措置を進めていることも伝えれば、企業側が違法行為に対して毅然とした対応をしていることを示すことができます。将来的に、信頼回復にも大きく役立つでしょう。
4、自社対応する場合と弁護士に依頼した場合の比較
ネット上の誹謗中傷への対応は、自社で対応することもできますが、迅速かつ適切に対応するためにも弁護士に依頼するのがおすすめです。
-
(1)慰謝料請求を自社対応するメリットとデメリット
慰謝料請求を自社対応すれば弁護士費用を支払う必要がなくなりますので、経済的な負担を抑えることができます。
しかし、ネット上の誹謗中傷の事案は、投稿者の特定のために発信者情報開示請求という手続きが必要になり、ログの保存期間が3~6か月と非常に短いため迅速な対応が必要になります。それには専門的な知識や経験が不可欠ですので、十分な知識のない企業の担当者では対応が難しいといえるでしょう。 -
(2)弁護士に依頼するメリットとかかる費用
ネット上の誹謗中傷問題について知見が豊富な弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、投稿者の特定のための発信者情報開示請求や投稿者に対する慰謝料請求の交渉・裁判などの手続きをすべて任せることができます。また、誹謗中傷の投稿の証拠保全をした後は、迅速に投稿の削除も行ってくれます。
法的かつネット上の誹謗中傷問題についての専門知識に基づいた対応が可能となり、誹謗中傷による被害回復に向けた対応をより効率的に行うことができる点が、弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。
なお、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用の支払いが必要になります。弁護士費用は、依頼する弁護士によって金額が変わりますが、おおむね、交渉のみで解決した場合は着手金と報酬金、そして郵送費などの事務手数料がかかり、発信者情報開示請求や訴訟に至った場合は、加えてそれらの必要費用などが追加されるケースがほとんどです。
目安として当事務所の費用相場は以下のリンクをご確認ください。 -
(3)ベリーベスト法律事務所の対応事例
ネット上の誹謗中傷によるトラブルに関して、当事務所が対応した事例を紹介します。
① 有名転職サイトにおける根拠のない誹謗中傷の口コミを削除した事例
A社は、有名転職サイト上に事実無根の口コミが投稿されてしまい、採用活動に悪影響が生じることを懸念して当事務所にご相談いただきました。
当事務所では、問題の口コミが投稿された有名転職サイトの削除請求の対応経験があったため、過去の交渉実績から裁判をしなくても交渉により削除に応じてくれるサイトであることを把握できていました。それにより迅速に削除請求をすることができ、削除請求から2週間程度で問題の口コミを削除することができました。
② スマホゲームの悪質クレームを顧問弁護士の対応で早期解決
A社は、スマホのオンラインゲームを制作・運営している会社です。不正操作により課金を免れたユーザーがいたため、アカウントを凍結したところ当該ユーザーがクレーマーと化して、掲示板に誹謗中傷の書き込みをしたり、A社に苦情のメールを大量に送付するようになったりしたため、当事務所に相談することになりました。
当事務所では、当該ユーザーに対して違法行為をやめるよう弁護士名で警告をしたところ、クレームが収まり早期解決となりました。
③ 出版社の特集記事を削除し謝罪文を掲載させた事例
Dさんは投資会社の社長をしており、とある雑誌でDさんが詐欺グループとかかわりがあるとの特集を発見しました。当該雑誌の出版社のホームページ上でもその特集と同じ内容が掲載されていたため、当事務所に相談することになりました。
当事務所では、Dさんからの依頼を受け、出版社を相手として、
・特集が誤りであると認め、雑誌に謝罪文を掲載すること
・ホームページの記事を削除すること
・慰謝料を支払うこと
を求める訴訟を提起しました。
最終的には、出版社側がホームページの特集記事を削除し、雑誌とホームページに謝罪文を掲載するとの条件で和解することができました。
5、まとめ
ネット上の誹謗中傷によるトラブルは、法律とIT技術について熟知している専門家に依頼することで、より適切な対応ができるケースが多いものです。
ベリーベスト法律事務所では、グループ内にITエンジニアが在籍しているだけでなく、SEO対策チームがありますので、弁護士と連携した総合的な対応を可能としています。
ネット上の誹謗中傷でお困りの企業の担当者や経営者の方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2025年07月23日)の法律をもとに執筆しています
同じジャンルのコラム【法人】誹謗中傷・風評被害
-
誹謗中傷・風評被害法人2025年07月23日更新
 インターネット上(以降「ネット上」と表記)での誹謗中傷は、企業に深刻な影響を与える可能性があります。ブランドイメージや従業員のモチベーションの低下、業績の悪化...
インターネット上(以降「ネット上」と表記)での誹謗中傷は、企業に深刻な影響を与える可能性があります。ブランドイメージや従業員のモチベーションの低下、業績の悪化... -
誹謗中傷・風評被害法人2025年06月16日更新
 一休.comは、ホテルや旅館、レストランなどの予約サービスを提供しています。当該サイトやアプリでは、施設を利用した方が口コミや画像を投稿可能です。そのため、高...
一休.comは、ホテルや旅館、レストランなどの予約サービスを提供しています。当該サイトやアプリでは、施設を利用した方が口コミや画像を投稿可能です。そのため、高... -
誹謗中傷・風評被害法人2025年05月19日更新
 美容医療クリニックを経営するうえで、Googleマップ、SNS、ポータルサイトなどの口コミは集客をするうえで無視できない存在です。好意的な口コミが多数掲載され...
美容医療クリニックを経営するうえで、Googleマップ、SNS、ポータルサイトなどの口コミは集客をするうえで無視できない存在です。好意的な口コミが多数掲載され...