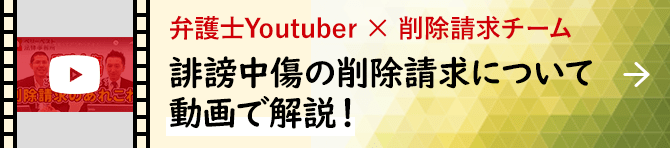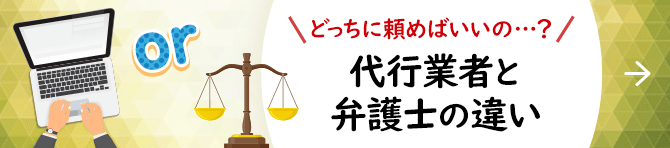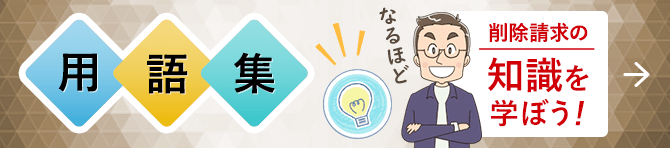開示請求・口コミ削除
SNSでの誹謗中傷、炎上、風評被害など
ネットトラブルのご相談は弁護士へ
弁護士コラム
- 削除依頼・投稿者の特定
- 全コラム一覧
- 【法人】誹謗中傷・風評被害
- ネット上の誹謗中傷について責任追及ができる根拠となる法律と対応方法を解説
-
Google口コミの
ネガティブ投稿 -
SNSでの
誹謗中傷 -
口コミサイトの
ネガティブ投稿
弁護士にご相談ください
お問い合わせに費用は発生しません。
安心してご連絡ください。
1、ネット上の誹謗中傷を規制する法律は?
法律では「誹謗中傷」について定義されていません。
一般的には、「公の場で行われる、他人の名誉を侵害したり不快感を与えたりする言動」が誹謗中傷とされています。
また、「インターネット上で誹謗中傷をしてはならない」と具体的に規定した法律もありません。
しかし、一般法である刑法・民法の規定に基づいて、加害者の責任を追及することはできるのです。
さらに、プロバイダ責任制限法では「発信者情報開示請求」が認められており、匿名で誹謗中傷を行った投稿者の個人情報を特定できるようになっています。
なお、プロバイダ責任制限法の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」です。
2、誹謗中傷の加害者に生じる法的責任
誹謗中傷の加害者には、以下のように、刑事責任と民事責任の両方が発生します。
-
(1)刑事責任|名誉毀損(きそん)罪・侮辱罪
インターネット上の誹謗中傷については、刑法上の「名誉毀損罪」(刑法第230条第1項)または「侮辱罪」(刑法第231条)が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し他人の名誉を毀損したこと」に対して適用される罪です。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。
名誉の成立要件は、具体的には、下記の通りになります。
<名誉毀損罪の成立要件>
① 公然と
不特定または多数の人に伝わる場所で発言等が行われたこと。
② 事実を摘示し
誹謗中傷を行う際、何らかの事実を提示したこと。
(例)「Aは不倫をしている人間のクズだ」
③ 他人の名誉を毀損したこと
他人の社会的評価を下げる性質の言動であること(実際に社会的評価が下がったかどうかは、問題ではない)。
また、以下の要件をすべて満たす場合には、違法性が阻却されて名誉毀損罪は不成立となるのです(刑法第230条の2)。
- 摘示された事実が公共の利害に関係すること
- 事実を摘示したのが、専ら公益を図る目的であったこと
- 摘示された事実が真実であると証明されたこと
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したこと」に対して適用される罪です。
具体的には、公然と他人の社会的評価を下げる性質の言動を行ったものの(上記①と③)、上記②の事実の摘示がなかった場合には、侮辱罪が成立します。
(例)「Aは人間のクズだ」
侮辱罪の法定刑は「拘留または科料」であり、名誉毀損罪よりもかなり軽いものになっています。 -
(2)民事責任|損害賠償・名誉回復措置
インターネット上での誹謗中傷は、被害者に対して精神的損害や社会的評価が毀損されることに伴う実害を与えるため、民法上の「不法行為」(民法第709条)に該当します。
そして、誹謗中傷の被害者は加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
さらに、誹謗中傷の投稿により被害者の名誉が毀損された場合、裁判所は被害者の請求に基づいて、名誉回復のための処分を加害者に命ずることができます(民法第723条)。
<名誉回復措置の例>
- 謝罪広告、取り消し広告、訂正広告等の掲載
- 誹謗中傷投稿の削除
なお、損害賠償請求と名誉回復措置は、併せて行うことも可能です。
3、ネット上で誹謗中傷された場合の相談先
上述したように、インターネット上で誹謗中傷された方は、法的措置によって被害回復を図ることができます。
しかし、法律の専門家でない方が自分だけで裁判手続き等の法的措置を講ずることは、難しい場合が多いものです。
インターネット上で誹謗中傷をされた方の相談窓口としては、公的機関・民間機関・弁護士などが存在します。お早めにご相談ください。
-
(1)総務省の「違法・有害情報相談センター」
総務省では、インターネット関連のトラブル全般について相談を受け付ける、「違法・有害情報相談センター」を設置しています。
(参考:違法・有害情報センターホームページ)
「違法・有害情報相談センター」には、インターネットに関する技術・制度などの専門的な知識と経験を有する相談員が常駐しています。
被害者自身で投稿の削除依頼を行う方法などについて、相談員からアドバイスを受けることが可能です。 -
(2)法務省の人権相談窓口
法務省では、人権侵害の被害者からの相談を受け付ける相談窓口を設置しています。
電話相談のほか、インターネット相談やLINEでの相談も受け付けています。
(参考:「人権擁護局フロントページ」(法務省))
違法な誹謗中傷については、法務局がプロバイダ等に対する削除要請を行うケースもあります。
ただし、法務局による違法性の判断には時間がかかってしまう場合が多い点に注意してください。 -
(3)セーファーインターネット協会の「誹謗中傷ホットライン」
「一般社団法人セーファーインターネット協会」は、インターネットの悪用防止などを目的として、民間によって設立された団体です。
セーファーインターネット協会では、誹謗中傷の被害者から相談を受け付ける「誹謗中傷ホットライン」を設置しています。
(参考:「誹謗中傷ホットライン」(一般社団法人セーファーインターネット協会))
誹謗中傷ホットラインは無料で利用することができ、違法な誹謗中傷に関する削除依頼を代行してもらうことも可能です。 -
(4)弁護士
上述したように、公的機関や民間機関の相談窓口が、誹謗中傷に関する一般的な相談や削除依頼について対応してくれる場合があります。
その一方で、各機関の窓口に相談することには、以下のようなデメリットも存在します。- 対応開始までに時間がかかるうえ、実際に動いてくれるかどうかわからない
- 加害者の特定や損害賠償請求については対応してもらえない
誹謗中傷による被害の回復を速やかに目指したいとお考えの方には、弁護士に相談することをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、代理人として迅速に対応を開始し、誹謗中傷の被害回復を図ります。
また、公的機関や他の民間機関とは異なり、依頼者の要望に応じて、あらゆる法的手段を講じることが可能です。
4、誹謗中傷に対して弁護士が行う法的対応
誹謗中傷の被害回復に向けて弁護士が行うことのできる法的な対応としては、以下のようなものがあります。
-
(1)投稿の削除請求
弁護士は、被害者からの依頼に応じて、加害者本人やサイト管理者に対して投稿削除を請求することができます。
弁護士から連絡されることで、加害者本人やサイト管理者が事の重大さを認識して、速やかな削除が実現できる可能性があります。
また、サイト管理者が削除請求に応じない場合には、裁判所に投稿削除の仮処分を申し立て、誹謗中傷投稿の強制的な削除を目指すこともできるのです。 -
(2)発信者情報開示請求
匿名での誹謗中傷投稿について、加害者である投稿者に損害賠償等を請求するためには、まずは投稿者を特定しなければなりません。
投稿者を特定するためには、「発信者情報開示請求」(プロバイダ責任制限法第4条第1項)が有効です。
誹謗中傷に関する損害賠償請求を行うために発信者情報の開示が必要な場合、裁判所に仮処分を申し立てたり訴訟を提起したりすることで、サイト管理者やインターネット接続業者から、投稿者の個人情報を取得することができます。
発信者情報開示請求の手続きは、多段階にわたる複雑なものとなっています。
依頼を受けた弁護士であれば、発信者情報開示請求を一括してサポートすることができます。 -
(3)損害賠償請求
加害者の特定が済んだ後、損害賠償請求を行う際にも、弁護士に依頼することをおすすめします。
加害者との示談交渉から、示談がまとまらなかった場合の訴訟に至るまで、損害賠償請求に必要なあらゆる手続きを弁護士が代行します。
弁護士がきちんとした証拠を準備して、加害者や裁判所に対して合理的な主張を展開することで、十分な金額の損害賠償を得られる可能性が高まるでしょう。 -
(4)刑事告訴のサポート
誹謗中傷の被害者は、損害賠償請求にとどまらず、「加害者には刑事処分による制裁も受けてほしい」と希望することもあるでしょう。
この点、刑事告訴の手続きについても、弁護士はサポートすることが可能です。
被害者が実際に受けている損害の深刻さを、弁護士が捜査機関に対して説得的に伝えることで、投稿者に対する捜査の開始や刑事訴追を促します。このように、弁護士はさまざまな方法により誹謗中傷の被害回復をサポートすることができます。
インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた方は、お早めに、弁護士までご相談ください。
5、まとめ
誹謗中傷の加害者は、刑法上の犯罪者として処罰される可能性があるとともに、被害者に対する損害賠償責任も負います。
もし誹謗中傷の被害を受けた場合、取り得る対処法を十分に検討するため、公的機関・民間機関・弁護士のいずれかにご相談ください。
特に、被害回復に向けた法律的な対応を迅速に行いたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、誹謗中傷の被害にあわれた方のために、法的な対処法に関するご相談を随時承っております。誹謗中傷投稿の削除依頼や、加害者に対する損害賠償請求等を検討したときは、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2022年06月23日)の法律をもとに執筆しています
同じジャンルのコラム【法人】誹謗中傷・風評被害
-
誹謗中傷・風評被害法人2022年06月23日更新
 インターネットで誹謗中傷されてしまうと、被害者は精神的なダメージを受けてしまうでしょう。また、誹謗中傷の投稿等を放置していると、風評被害が拡大してしまいかねま...
インターネットで誹謗中傷されてしまうと、被害者は精神的なダメージを受けてしまうでしょう。また、誹謗中傷の投稿等を放置していると、風評被害が拡大してしまいかねま... -
誹謗中傷・風評被害法人2022年05月26日更新
 YouTubeでは、企業が販売する商品の紹介などもよく行われています。YouTube視聴者は近年爆発的に増加しているため、コメント機能を通じて投稿される口コミ...
YouTubeでは、企業が販売する商品の紹介などもよく行われています。YouTube視聴者は近年爆発的に増加しているため、コメント機能を通じて投稿される口コミ... -
誹謗中傷・風評被害法人2021年12月08日更新
 病院に所属している医師・看護師等は、日々多くのの患者及びその家族と向き合っているため、その患者や家族の中からネガティブな意見をネット上に投稿する方が出てきてし...
病院に所属している医師・看護師等は、日々多くのの患者及びその家族と向き合っているため、その患者や家族の中からネガティブな意見をネット上に投稿する方が出てきてし...