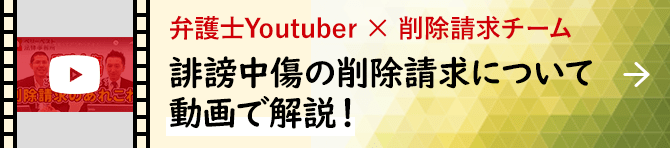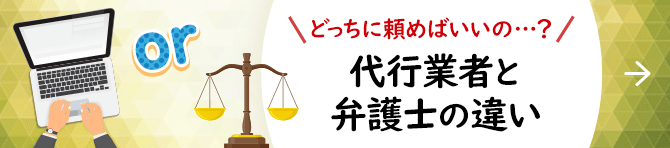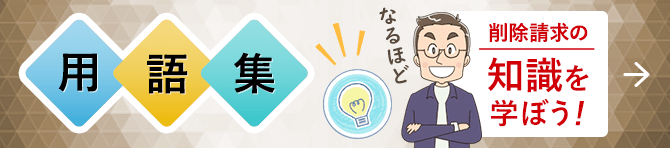削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
弁護士コラム
- 削除依頼・投稿者の特定
- 全コラム一覧
- 【法人】名誉毀損
- ネット上で会社や店の名誉を毀損された! 相手を訴える条件はある?
-
名誉毀損法人2025年02月18日更新

ネット上で会社や店の名誉を毀損された! 相手を訴える条件はある?
インターネットやSNSが発展し、パソコンやスマートフォンを利用して誰でも自由にインターネット上に投稿ができるようになってきました。いつでも簡単に情報を入手できることは消費者にとっては好ましいといえますが、インターネット上に悪意のある書き込みがなされると会社やお店の名誉毀損となるケースも増えてきています。
インターネット上の情報は、内容の真偽を問わずあっという間に拡散してしまいますので、誹謗中傷の投稿がなされてしまうと売り上げの減少や企業・お店の信用性低下などのリスクが生じますので、早期に対応する必要があります。
今回は、インターネット上で会社やお店の名誉が毀損された場合に、相手を訴える条件やその流れなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、ネット上で会社や店の名誉を毀損された場合、まず何をすべき?
インターネット上で会社やお店の名誉を毀損された場合、何から手を付ければよいのでしょうか。以下では、名誉毀損された場合の初動について説明します。
-
(1)名誉毀損で訴えるための証拠を集める
インターネット上で会社やお店の名誉を毀損された場合、加害者を名誉毀損で訴えることができます。そのためには、名誉を毀損されたことを客観的に立証しなければなりませんので、まずは必要な証拠を集めるようにしてください。
名誉毀損で訴えるための証拠は、事案によって異なりますが、代表的なものとしては以下のような証拠が挙げられます。- 名誉毀損となる投稿のスクリーンショット
- 投稿者のアカウントのプロフィルのスクリーンショット
名誉毀損の投稿は、すぐに削除されてしまうこともありますので、名誉毀損になる可能性のある投稿を発見したときは、すぐにスクリーンショットにより保存するようにしましょう。その際には、投稿されたページのURLおよび投稿日時などがわかるように、保存することがポイントです。 -
(2)すぐに弁護士に相談する
インターネット上で名誉毀損となる投稿を発見したときは、スクリーンショットを撮影したすぐ後に、弁護士に相談するようにしてください。
名誉毀損の投稿をした相手を訴えてスムーズな解決を目指すには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。弁護士であれば、当該口コミや投稿を削除できるか判断でき、その後投稿者を特定し、民事・刑事両方の責任を問うための手段を熟知しています。
インターネット上での名誉毀損に対しては、迅速な対応が必要になりますので、できるだけ早く弁護士に相談するようにしましょう。
2、そもそも、名誉毀損とは? 名誉毀損で訴えることができる条件とは?
そもそも名誉毀損とは、どのような行動を指すのでしょうか。また、名誉毀損で訴えるためにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。
-
(1)名誉毀損(棄損)とは?
名誉毀損(棄損)とは、公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為です。公表した事実が真実、虚偽どちらであったとしても、法律に定められた条件を満たせば、名誉毀損(棄損)に問われる可能性があります。
民事上の名誉毀損が成立するケースでは加害者に対して損害賠償請求をすることができ、刑事上の名誉毀損が成立するケースでは、刑事告訴により刑事罰の対象とすることができます。
そこで、以下では、民事と刑事の成立条件をそれぞれ説明します。 -
(2)刑事事件で名誉毀損罪となる条件
刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)が成立する場合には、投稿者に対して刑事上の責任追及が可能です。
名誉毀損罪が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。- 公然性があること(不特定または多数の人が認識可能であること)
- 事実を摘示したこと
- 人の名誉を毀損したこと
たとえば、インターネット上で「株式会社○○は、暴力団とつながりがある」、「○○という店は、賞味期限切れの商品を提供している」などの虚偽の事実を投稿した場合、名誉毀損罪の成立要件を満たしますので、刑事上の責任追及をすることができます。
ただし、以下すべての基準を満たす投稿については、違法性がないと判断がされますので、名誉毀損罪は成立しません(刑法230条の2第1項)。- ① 事実の公共性
- ② 目的の公益性
- ③ 摘示した事実が真実であること
また、①②の成立を前提に、③の証明ができない場合でも、④行為者(投稿者)がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときにおいても、名誉毀損罪は成立しません(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁、最決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁)。④を理由とした名誉毀損罪の不成立は、事実の投稿の際に投稿者が十分な真偽の調査をしている場合に認められるものであり、根拠のない誤信に基づく投稿を許容するものではありません。
-
(3)民事事件で名誉毀損と認められる条件
名誉毀損による民事上の責任を問うためには、不法行為(民法709条)が成立するための条件を満たす必要があります。
- 投稿に違法性があること
- 投稿者に故意または過失が認められること
- 投稿により被害者に損害が発生したこと
このうち投稿の違法性については、基本的には前述の名誉毀損罪と同様の枠組みで判断されます。すなわち、不特定または多数の人が認識できる状態で他人の社会的評価を低下させるような投稿がなされることをいいます。被害者の社会的評価を低下させるおそれのある事実を記載した投稿をインターネット上で公開する行為は、他人の名誉を毀損する違法な投稿といえますので、民事上の名誉毀損の条件を満たすといえます。
もっとも、以下すべての基準を満たす投稿については、違法性が無いと判断され、不法行為にはならない場合があります(最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁等)。- ① 事実の公共性
- ② 目的の公益性
- ③ 摘示した事実が真実であること、または重要な部分を真実であると信じることに相当の理由があること
3、民事で名誉毀損の責任を問う
以下では、民事で名誉毀損の責任を問う場合の内容や流れについて説明します。
-
(1)民事事件で実現できること
インターネット上での名誉を毀損された場合、以下のような手段により被害の回復を図ることができます。
① 損害賠償請求
インターネット上での名誉毀損により不法行為が成立する場合には、加害者に不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
損害とは、慰謝料、すなわち、精神的損害のことをいいます。法人であっても慰謝料を請求することができます。精神的損害の発生の有無及びその程度は、社会的評価により客観的類型的にとらえられます。
② 名誉回復措置
名誉毀損の被害を受けた場合、謝罪広告の掲載などの名誉を回復するための必要な措置を求めることができます。
インターネット上での名誉毀損は、情報が拡散されることで深刻な被害を受けるケースも多いため、損害賠償請求だけでは被害を回復することができないことがあります。そのようなケースについては、損害賠償請求に加えて名誉回復措置を検討しましょう。
③ 削除請求
インターネット上で名誉毀損の投稿がなされた場合、それを放置すると多くの人の目に触れることになりますので、被害がどんどん拡大してしまいます。
そのため、名誉毀損による被害を最小限に抑えるためにも投稿の削除を求める必要があります。 -
(2)名誉毀損の責任を問う民事訴訟の流れ
名誉毀損の投稿をした加害者に対して民事上の責任を問う場合、以下のような流れで手続きを進めていきます。
① 発信者情報開示請求により加害者の特定
加害者に対して民事上の責任追及をする前提として、まずは加害者を特定しなければなりません。インターネット上での名誉毀損は、基本的には匿名で行われますので、投稿自体からは加害者を特定することができません。
そこで、発信者情報開示請求や発信者情報開示命令という手続きにより加害者を特定する必要があります。
② 民事訴訟の提起
加害者が特定できたら、加害者に対して民事訴訟を提起します。
訴訟では、被害者の側において、加害者による名誉毀損があったことを主張立証していかなければなりません。
裁判所に被害者側の主張が認められれば、加害者に対して損害賠償金の支払いを命じる判決が言い渡されます。
③ 強制執行の申し立て
判決確定後も加害者が損害賠償金の支払いをしない場合は、裁判所に強制執行の申し立てを行います。強制執行の申し立てをすることで、相手の財産から強制的に未払いとなっている賠償金を回収することができます。
4、刑事で名誉毀損の責任を問う
以下では、名誉毀損の刑事責任を問う場合の内容や流れについて説明します。
-
(1)刑事事件で実現できること
名誉毀損罪が成立する場合、加害者には
・3年以下の懲役もしくは禁錮
または
・50万円以下の罰金
が科されます(刑法230条1項)。
刑事事件は、民事事件とは異なり被害者が直接加害者に対して責任追及をするわけではありません。捜査機関により立件され、刑事裁判により刑罰が科されることになります。
ただし、名誉毀損罪は親告罪(被害者が申告しなければ罰せられない罪)(刑法232条1項)ですので、加害者に対する適正な刑罰を実現するには、被害者による告訴が必要です。 -
(2)名誉毀損罪と類似する他の犯罪
インターネット上で誹謗中傷があった場合に成立する犯罪は、名誉毀損罪以外にも以下のような犯罪があります。
① 侮辱罪
侮辱罪とは、事実を摘示することなく公然と人を侮辱することで成立する犯罪です(刑法231条)。
名誉毀損罪は事実の摘示が必要になりますが、侮辱罪は事実の摘示が不要という点で両者は区別されます。
なお、侮辱罪が成立すると以下のいずれかの刑罰が科されます。- 1年以下の懲役または禁錮
- 30万円以下の罰金
- 拘留
- 科料
② 信用毀損罪
信用毀損罪とは、虚偽の風説の流布または偽計を用いることで、人の信用を毀損する犯罪です(刑法233条)。
名誉毀損罪は、人の社会的評価を低下させる犯罪ですが、信用毀損罪は人の経済的に信用を低下させる犯罪であるという点で両者は区別されます。
なお、信用毀損罪が成立すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
③ 偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは、偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です(刑法233条)。
名誉毀損罪は、摘示された事実が真実であるかどうかは問われませんが、偽計業務妨害罪は流布された事実が真実と異なることが必要であるという点で両者は区別されます。
なお、偽計業務妨害罪が成立すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。 -
(3)刑事裁判の流れ
民事事件では、被害者が主体となって加害者に対して責任追及を行いますが、刑事事件において加害者に対する責任追及を行うのは、警察や検察といった捜査機関です。そのため、具体的な責任追及の手続きは、基本的には捜査機関に委ねることになります。
ただし、名誉毀損罪は被害者による告訴が必要であるため、加害者に対する刑事責任の追及をするには被害者が告訴をしなければなりません。
5、まとめ
インターネット上で名誉毀損をされると企業やお店には、さまざまな悪影響が生じますので、早期に対応する必要があります。
ベリーベスト法律事務所では、問題の投稿や口コミ1件からの削除請求対応も可能です。また、今後の対策も必要であれば、顧問契約という方法で対策をすることもできます。さらに、顧問弁護士契約は、月額3980円から対応しており、全国各地に拠点があるため全国に支社や支店を有する企業でも相談しやすいのが特徴です。インターネット上での名誉毀損行為にお困りの経営者の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
風評被害にお困りの方は、ぜひ以下のページもご覧ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2025年02月18日)の法律をもとに執筆しています
同じジャンルのコラム【法人】名誉毀損
-
名誉毀損法人2025年02月18日更新
 インターネットやSNSが発展し、パソコンやスマートフォンを利用して誰でも自由にインターネット上に投稿ができるようになってきました。いつでも簡単に情報を入手でき...
インターネットやSNSが発展し、パソコンやスマートフォンを利用して誰でも自由にインターネット上に投稿ができるようになってきました。いつでも簡単に情報を入手でき... -
名誉毀損法人2023年02月21日更新
 ネット上で散見する、根拠のないネガティブな書き込みは、場合によっては大きな被害を受けてしまうことになりかねません。名誉毀損となり得る中傷への対応は、大企業だけ...
ネット上で散見する、根拠のないネガティブな書き込みは、場合によっては大きな被害を受けてしまうことになりかねません。名誉毀損となり得る中傷への対応は、大企業だけ... -
名誉毀損法人2021年10月04日更新
 新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて、医療機関や医療従事者の方への誹謗中傷が社会問題化しています。全国の自治体でも人権への配慮などを呼び掛けるとともに、コロ...
新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて、医療機関や医療従事者の方への誹謗中傷が社会問題化しています。全国の自治体でも人権への配慮などを呼び掛けるとともに、コロ...