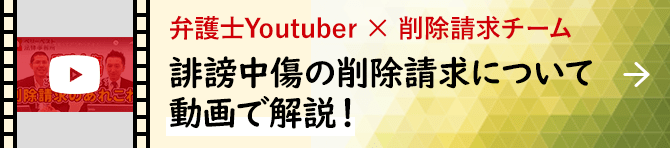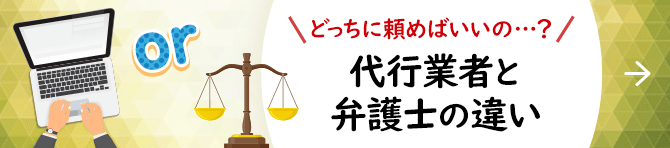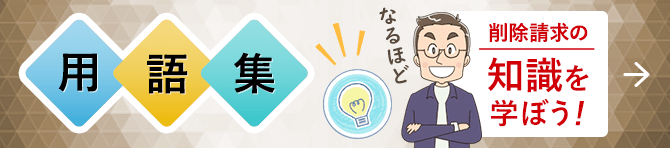開示請求・口コミ削除
SNSでの誹謗中傷、炎上、風評被害など
ネットトラブルのご相談は弁護士へ
弁護士コラム
- 削除依頼・投稿者の特定
- 全コラム一覧
- 【法人】発信者情報開示請求
- 会社への誹謗中傷をどうにかしたい! 対処方法や収集すべき証拠とは
-
発信者情報開示請求法人2025年09月01日更新

会社への誹謗中傷をどうにかしたい! 対処方法や収集すべき証拠とは
SNSや掲示板などで企業などに対する誹謗中傷の投稿が見つかったときは、そのまま放置するのではなく、すぐに投稿の削除を求めるなどの適切な対応をとる必要があります。
また、すでに誹謗中傷の投稿が拡散されており、企業イメージの低下や顧客離れ、売上の減少といった損害が発生している場合、誹謗中傷の投稿者に対してその損害賠償請求などの対応を検討することもあるでしょう。
その際に重要になるのが、誹謗中傷の事実や投稿内容によって生じた被害を証明できる証拠です。証拠がなければ投稿者やサイトの管理者などへの法的な請求が困難となるため、適切な証拠を集めるポイントを押さえておきましょう。
本コラムでは、企業への誹謗中傷があったときに収集すべき証拠や対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
-
Google口コミの
ネガティブ投稿 -
SNSでの
誹謗中傷 -
口コミサイトの
ネガティブ投稿
弁護士にご相談ください
お問い合わせに費用は発生しません。
安心してご連絡ください。
1、誹謗中傷を証明するために集めるべき証拠と注意点
SNSや掲示板への投稿者に対して、誹謗中傷を受けたことを理由に損害賠償等を請求するには、誹謗中傷されたという事実や投稿内容によって生じた被害を証明するための証拠が重要です。
最初に、誹謗中傷を証明するために集めるべき証拠と注意点を説明します。
-
(1)誹謗中傷を証明するために集めるべき証拠
企業への誹謗中傷で、損害賠償等を請求するために収集すべき証拠は、大きく分けて「誹謗中傷の事実を証明する証拠」と「誹謗中傷により生じた被害を証明する証拠」の2種類があります。
① 誹謗中傷の事実を証明する証拠
誹謗中傷の事実を証明する証拠としては、以下のようなものを収集しましょう。誹謗中傷の投稿のスクリーンショット
- SNS(X、Instagram、Facebookなど)、掲示板、ブログなどの投稿画面を撮影する
- 投稿日時、ユーザー名、URL、投稿内容を確認できるようにする
URL・投稿IDの保存
- 投稿のURLやユーザーID、ハンドルネームなどを控えておく
- 誹謗中傷の投稿と一緒に写るように撮影する
サイト内容(記事ページなど)の保存
- ウェブ魚拓やInternet Archiveでページを保存する
SNSや掲示板、ブログなどでの誹謗中傷の投稿を証拠化する際には、単に誹謗中傷の投稿だけを保存すればよいというわけではなく、投稿日時・ユーザー名・URLなどがわかるように保存するのがポイントです。
また、サイト内容をウェブ魚拓などで保存しておく方法は、サイトの改変や削除された場合に有効で、改ざんが疑われにくい有力な証拠となります。
② 誹謗中傷により生じた被害を証明する証拠
誹謗中傷により生じた被害を証明する証拠としては、以下のようなものが挙げられます。法人の場合
- 帳簿や取引データ:誹謗中傷の投稿により売上が減少したことを証明するための証拠
- 取引先からの契約解除通知:誹謗中傷が理由で取引先から契約を打ち切られたことを証明するための証拠
- GoogleのレビューやSNSのコメント:誹謗中傷の投稿後から、企業への悪評が増えたことを証明するための証拠
個人の場合
- 医師の診断書、通院記録:誹謗中傷の投稿により精神的苦痛を被ったことを証明するための証拠
- 治療費などの領収書:誹謗中傷による治療費の金額を証明するための証拠
- 休職証明書:誹謗中傷により仕事を休んで収入が減少したことを証明するための証拠
- 解雇理由証明書:誹謗中傷による精神的苦痛が原因で働けなくなったことや、誹謗中傷に関する事実それ自体を理由に解雇されたことを証明するための証拠
個人・法人共通
- 弁護士費用の領収書:誹謗中傷の投稿者を特定するために支出した、弁護士費用の金額を証明するための証拠
誹謗中傷の投稿があった場合、その誹謗中傷と上記の各損害との間の因果関係が認められれば、法人であれば慰謝料や営業損害などの損害を、個人であれば慰謝料や治療費などの損害を請求できる可能性があります。
なお、投稿者を特定するために必要になった弁護士費用については、調査費用として投稿者に請求できる可能性があります。 -
(2)誹謗中傷の証拠を集める際の注意点
誹謗中傷の証拠を集める際には、以下の点に注意して、確実な証拠確保を心がけましょう。
① 誹謗中傷の証拠は早めに保存する
誹謗中傷の投稿を見つけたときは、すぐに証拠を保存するようにしてください。
誹謗中傷の投稿がSNSや掲示板上で拡散・炎上した場合、投稿者が責任追及を恐れて投稿やアカウントを削除することがあります。証拠を確保する前に問題の投稿が削除されてしまうと、誹謗中傷の投稿をした本人を特定することができなくなるため、早めに証拠を保存しておくことが大切です。
② 証拠を確保後、すぐに投稿者を特定する手続きを始める
誹謗中傷の証拠を確保したら、すぐに投稿者の特定の手続きを始めるようにしてください。誹謗中傷の投稿者を特定するためには、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダへの発信者情報開示請求が必要になりますが、特にアクセスプロバイダが保有する投稿者の特定に必要となるアクセスログには、プロバイダごとに保存期間があります。
アクセスログの保存期間が経過してログが消えてしまうと、誹謗中傷の証拠があったとしても投稿者の特定が不可能になるため、速やかな法的手続きの準備が不可欠です。なお、ログ保存期間は、短いプロバイダでは3か月程度、長いプロバイダでは半年から1年程度とされていることもありますが、その誹謗中傷の投稿が具体的にどのアクセスプロバイダ経由でされているかは手続きが進まないとわからないため、ログ保存期間が短いプロバイダで投稿されたと想定して対応するのが望ましいです。
③ 証拠が不十分だと、責任追及が困難になる
下記のいずれの手続きにおいても、誹謗中傷の証拠が欠かせません。- 誹謗中傷の投稿者を特定するための手続き(発信者情報開示請求)
- 損害賠償など民事上の責任を追及する手続き
- 名誉毀損罪や侮辱罪など、刑事責任を問うための刑事告訴手続き
証拠が不十分である場合、投稿者の特定ができず、民事・刑事のいずれの責任追及も困難になります。被害回復の機会を逃さないためにも、証拠収集は慎重かつ計画的に行いましょう。
2、誹謗中傷の投稿で検討すべき3つの民事的対応
2章では、誹謗中傷の投稿がなされたときに考えられる3つの民事的対応について、解説します。
-
(1)削除要請
誹謗中傷の投稿を見つけたときは、まずは証拠を保存したうえで、速やかに削除要請をするようにしてください。
投稿を削除するために考えられる方法 - サイト管理者に対する任意の削除依頼(初期対応として有効)
- 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく送信防止措置請求(法的な削除請求)
- 裁判所への仮処分申し立て(迅速な削除命令を求める法的措置)
誹謗中傷の投稿をそのまま放置していると、企業に対する悪評が広がり、イメージの低下や顧客離れ、それに伴う売上の減少といった損害が発生する可能性があります。時間が経てば経つほど、これらの悪影響が生じるリスクが高くなっていくため、早期に問題の投稿の削除に向けた対応をとるべきです。
なお、投稿の削除は、その投稿がなされたサイトの管理者やプロバイダに対して請求することが可能であるため、必ずしも投稿者が誰であるか特定しておく必要はありません。 -
(2)謝罪文掲載の要求
誹謗中傷の投稿により名誉毀損をされた場合、名誉回復措置の一環として、加害者に対し謝罪文の掲載を求めることが認められています(民法723条)。任意の交渉で話に応じてくれないときは、裁判による解決を図ることが可能です。
謝罪文の掲載を要求するには、誹謗中傷の投稿をした本人を特定する必要があるため、「発信者情報開示請求」という手続きを行わなければなりません。
これについて、詳細は本コラム4章の「発信者情報開示を行うための手続きの進め方」をご覧ください。 -
(3)損害賠償請求
誹謗中傷の投稿により権利を侵害された場合、加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。投稿者の特定後、主に慰謝料や営業損害などを請求していくことになるでしょう。
基本的な流れは謝罪文掲載の要求と同様で、発信者情報開示請求によって投稿者を特定した後、損害賠償請求に進むことになります。
3、誹謗中傷の投稿で考えられる3つの刑事的責任
悪質な誹謗中傷の投稿があったときは、刑事告訴により加害者に対する刑事責任を追及していくことも考えられます。インターネット上の誹謗中傷で成立しうる罪としては、主に以下のようなものが挙げられます。
-
(1)名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、公然と他人の社会的評価を低下させ得る事実を摘示した場合に成立する犯罪です(刑法230条)。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことをいい、SNS・掲示板・ブログなどでの誹謗中傷であれば、通常は誰でも閲覧可能な状態であるため、公然性の要件を満たします。
企業への名誉毀損罪が成立する典型例としては、以下のような投稿が挙げられます。事実無根で社会的評価を下げるような書き込み
「○○会社は反社とつながっているから利用しないほうがいい」「○○プロダクションのイベントに参加すると必ず痴漢に遭うし、犯罪の温床」「○○店は廃棄寸前の腐りかけた食材を使った料理を提供している」など、真実でない事実をSNSや掲示板で拡散する投稿
なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑(旧:懲役・禁錮)または50万円以下の罰金と定められています。
-
(2)侮辱罪
侮辱罪とは、事実を摘示せずに公然と人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。
「侮辱」とは、人に対する侮蔑的な価値判断を表示することで、名誉毀損罪との違いは、事実の摘示があるかどうかです。事実の摘示を伴って他人の名誉を毀損する場合が名誉毀損罪で、事実の摘示を伴わない場合が侮辱罪となります。
企業への侮辱罪が成立し得る投稿としては、以下のような投稿が挙げられます。- 具体的な事実を適示せずに評価を貶める情報をネット上に流す
「○○は対応が最悪の詐欺会社」「○○は悪徳商法の会社なので注意」など、具体的な事実を示さない投稿 - 容姿に関する書き込み
「○○会社は化粧品会社のくせに全員ブス」「○○健康食品の従業員はデブばかり」など、容姿を侮辱する投稿
なお、侮辱罪の法定刑は、1年以下の拘禁刑(旧:懲役・禁錮)もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料と定められています。
- 具体的な事実を適示せずに評価を貶める情報をネット上に流す
-
(3)業務妨害罪
業務妨害罪とは、虚偽の情報を広めたり、人の錯誤や不知を用いたりする(偽計)などして、他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です(刑法233条、234条)。特にこのような方法による場合には、偽計業務妨害罪が成立します(刑法233条)。
企業への偽計業務妨害罪が成立する典型例としては、以下のような投稿が挙げられます。- 虚偽の情報をネット上に流す
「この店の食品に虫が入っていた」「〇〇会社は詐欺をしている」「〇〇プロダクションは裏で反社とつながってる」など、事実に反する内容をSNSや掲示板で拡散する行為 - バイトテロ
飲食店のアルバイトが食品を不衛生に扱う動画など、店舗や企業の信用を著しく毀損する投稿
なお、業務妨害罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑(旧:懲役・禁錮)または50万円以下の罰金と定められています。
- 虚偽の情報をネット上に流す
4、発信者情報開示を行うための手続きの進め方
誹謗中傷の投稿者を特定するには、発信者情報開示請求の手続きが必要です。以下では、発信者情報開示請求の概要と手続きの流れについて説明します。
-
(1)発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、インターネット上の誹謗中傷等の投稿をした人物を特定するために、サイト管理者やプロバイダに対して保有する投稿者の情報の開示を求める法的手続きをいいます。
インターネット上の誹謗中傷は、基本的には匿名で行われることが多いため、投稿内容そのものから投稿者を直接特定することは困難です。
しかし、匿名であっても「発信者情報開示請求」という手続きをとることにより、匿名の投稿者を特定することができます。 -
(2)発信者情報開示請求の手続きの流れ
誹謗中傷の投稿がなされたときは、以下のような流れで発信者情報開示請求の手続きを進めていきます。
① サイト管理者に対する発信者情報開示請求
まずは誹謗中傷の投稿がなされたサイトの管理者に対して、IPアドレス・タイムスタンプや、登録されている氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の開示を求めていきます。
弁護士からの発信者情報開示請求であれば、任意の開示に応じる可能性が高まるため、迅速に情報開示を受けるためにも、弁護士に依頼するのがおすすめです。
② サイト管理者に対する発信者情報開示仮処分命令または発信者情報開示命令の申し立て
サイト管理者が任意に発信者情報の開示に応じてくれないときは、裁判所に、サイト管理者に対して発信者情報の開示を求める仮処分命令、または発信者情報開示命令の申し立てを行います。
どちらも、サイトの管理者等に、保有している発信者情報の開示を求める裁判所の手続きです。そして、特に大手SNSなどのサイトの管理者は、どちらの手続きにしても裁判所の判断には従うことがほとんどであるため、裁判所が開示を命じた場合には、最終的には発信者情報が開示することがほとんどです。
それぞれの手続きの違いは、開示を求めることができる情報の範囲、手続きの内容、サイト管理者が裁判所の命令に従わない場合にとれる措置にありますが、ここでは裁判所の命令に従わない場合の措置を詳しく説明します。
裁判所が発信者情報の開示を命じたにもかかわらず、サイト管理者が情報を開示しない場合は、サイト管理者に対し、開示するまで1日あたりいくら支払え、という形で強制執行をすることになります(間接強制)。この間接強制の申し立ては、開示命令に基づいても、仮処分決定に基づいてもすることはできますが、問題はいつ間接強制の申し立てができるかということです。
開示命令に基づいて行う場合、開示命令の告知があってから1か月以内にサイト管理者側から不服申し立て(即時抗告)がなければ開示命令が確定し、ようやく間接強制の申し立てができます。逆にいえば、開示命令がなされてから開示されるまで、何もできないまま1か月以上待たなければならないことがあるということです。
他方、仮処分決定に基づいて行う場合、仮処分決定が送達されればすぐに間接強制の申し立てができるため、サイト管理者に開示を急がせることができます。
この②で行う手続きは、次の③のプロバイダを特定して、プロバイダに対して請求するために必要な情報を獲得するための手続きですので、③のプロバイダのログ保存期間に間に合うように開示を受ける必要があります。そのため、裁判所の命令にもかかわらず、サイト管理者が速やかに情報を開示してこないことが見込まれる場合には、発信者情報開示の仮処分命令の申し立ての手続きによる方がよいということになります。
これに対し、サイト管理者が比較的速やかに情報を開示してくると見込まれる場合は、②と③を一連の手続きで行うことのできる発信者情報開示命令の申し立ての手続きの方が適しているかもしれません。
③ プロバイダに対する発信者情報開示命令の申し立てまたは訴訟の提起
サイト管理者から開示されたIPアドレスおよびタイムスタンプを元に投稿者が利用したプロバイダを特定したら、次は、プロバイダに対する発信者情報開示請求を行います。
プロバイダは、任意での発信者情報開示に応じることはほとんどなく、裁判所の決定には従うということが多いです。そのため、発信者情報開示命令の申し立て、または訴訟の提起により、プロバイダに対して情報開示を求めます。
ここで、②の段階で発信者情報開示命令を申し立てている場合は、サイト管理者からプロバイダに直接IPアドレス等を提供するよう求めることもでき(提供命令)、一連の手続きとして対応することもできます。また、②の段階で仮処分命令の申し立てで情報の開示を受けていても、プロバイダに対して開示命令の申し立てをすることもできます。
請求が認められるか否かが際どく、時間をかけて審理する方が望ましいという事件でもなければ、迅速に解決できる発信者情報開示命令の申し立てによる場合が多いです。裁判所から発信者情報の開示が命じられれば、プロバイダから投稿者の住所や氏名などの情報が開示されます。
5、まとめ
企業に対する誹謗中傷の投稿が確認されたときは、すぐに証拠を保存の上、問題の投稿の削除を求めるよう対応すべきです。また、投稿者に対しては、損害賠償請求や刑事告訴をすることができるため、証拠を保存後、民事および刑事上の責任追及の手続きを進めていくとよいでしょう。
ただし、インターネット上の匿名での誹謗中傷の事案では、投稿者を特定するための発信者情報開示請求の手続きが必要になることが多いです。迅速かつ適切に対応を進めていくには、弁護士のサポートが不可欠です。
ベリーベスト法律事務所では、削除対応の経験・知見豊富な弁護士が在籍しています。Zoomなどを活用したオンラインでのご相談も可能ですので、まずは当事務所まで、お気軽にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。
誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。
※記事は公開日時点(2025年09月01日)の法律をもとに執筆しています
同じジャンルのコラム【法人】発信者情報開示請求
-
発信者情報開示請求法人2025年09月01日更新
 SNSや掲示板などで企業などに対する誹謗中傷の投稿が見つかったときは、そのまま放置するのではなく、すぐに投稿の削除を求めるなどの適切な対応をとる必要があります...
SNSや掲示板などで企業などに対する誹謗中傷の投稿が見つかったときは、そのまま放置するのではなく、すぐに投稿の削除を求めるなどの適切な対応をとる必要があります... -
発信者情報開示請求法人2025年03月06日更新
 店舗や施設のGoogleマップに悪質な口コミなどを書き込まれてしまうと、社会的信用の損失、売り上げの低下といった実害につながる可能性があるため、迅速かつ適切に...
店舗や施設のGoogleマップに悪質な口コミなどを書き込まれてしまうと、社会的信用の損失、売り上げの低下といった実害につながる可能性があるため、迅速かつ適切に... -
発信者情報開示請求法人2022年12月16日更新
 5ちゃんねるに会社、病院、飲食店などの悪口を書き込まれると、風評被害によってその法人の売り上げが減少するリスクがあるだけでなく、廃業に追い込まれてしまう可能性...
5ちゃんねるに会社、病院、飲食店などの悪口を書き込まれると、風評被害によってその法人の売り上げが減少するリスクがあるだけでなく、廃業に追い込まれてしまう可能性...