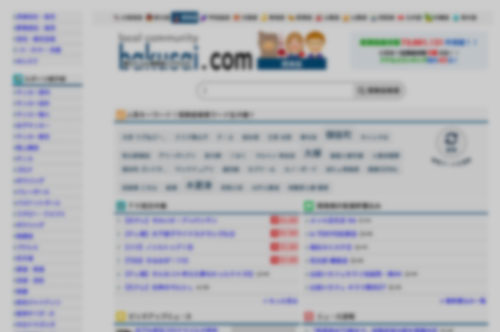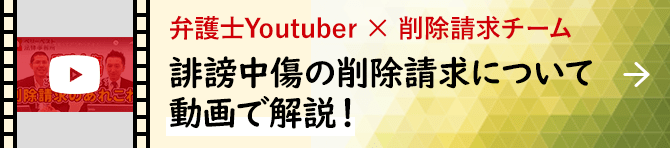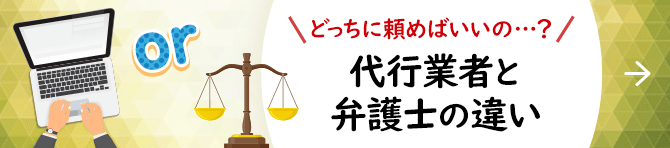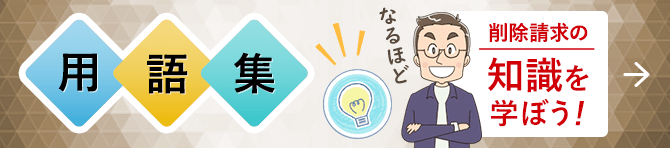削除依頼・投稿者の特定
5ちゃんねるや2ちゃんねるなどへの
悪質な書き込み削除のご相談は弁護士へ
削除依頼・投稿者の特定に関する
用語集
刑事告訴とは
読み方 けいじこくそ
刑事告訴
1、刑事告訴とは
刑事告訴とは、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
犯罪の捜査は、捜査機関である警察官や検察官が犯罪の発生を知ったときに開始されます。刑事告訴は、捜査機関が犯罪発生を疑い、捜査を開始するに至る捜査の端緒のひとつとして挙げられるものです。
一定の犯罪については、親告罪といって、被害者の意思を尊重し、被害者からの告訴がなければ犯人を起訴することができないとされています。また、親告罪以外の犯罪であっても、犯人の処罰について犯罪被害者などの意思を反映させることによって、犯罪の抑止や犯罪被害者保護を図る目的から,被害者がいる犯罪について犯罪の類型による限定を付すことなく,犯罪被害者などが刑事告訴をすることができると定められています(刑事訴訟法230条)
2、ネット上のトラブルで刑事告訴できるケース
インターネット上のトラブルで刑事告訴をすることができる代表的なケースとしては、以下のものが挙げられます。
(1)名誉毀損罪
公然と事実を摘示することによって他人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせた場合には、名誉毀損罪が成立します(刑法230条1項)。
たとえば、SNSなどで「○○さんは△△さんと不倫をしている」、「○○さんは××罪で逮捕されたことがある」などの投稿があった場合、それによって名誉を毀損された被害者は、刑事告訴をすることができます。
(2)信用毀損罪
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて人の信用を毀損したりした場合には、信用毀損罪が成立します(刑法233条)。
たとえば、ブログなどで「あの会社はもうすぐ倒産しそうだ」などの投稿があり、経済的な信用を毀損された被害者は、刑事告訴することができます。
(3)偽計・威力業務妨害罪
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて人の業務を妨害したり場合には、偽計業務妨害罪が成立します(刑法233条)。また、威力を用いて人の業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立します。
たとえば、インターネット上の口コミなどで「○○の商品には異物が混入している」、「○○に爆弾を仕掛けた」、「近々殺しに行く」などの投稿によって業務を妨害された被害者は、刑事告訴が可能です。
(4)侮辱罪
事実を摘示していなくても、公然と人を侮辱した場合は、侮辱罪が成立します(刑法第231条)。
たとえば、インターネット上の掲示板で「○○はバカだ」「○○は役立たず」「○○は死んだほうがまし」などの言葉を書き込みされたとき、刑事告訴ができる可能性が出てきます。
3、ネットトラブルで刑事告訴するときの注意点と手順
ネットトラブルで刑事告訴をする場合には、以下のような方法で行います。
(1)告訴権者が告訴する
告訴をすることができるのは、告訴権者に限られます。告訴権者は、刑事訴訟法230条から234条においてその範囲が定められていますが、典型的な告訴権者は、犯罪の被害者です。友人や知人では代理で告訴することはできません。
(2)告訴できる期間
告訴することができる期間は、親告罪については、犯人を知った日から6か月間とされています。親告罪以外の犯罪については、告訴期間は定められていません。
たとえば、名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪にあたるため、犯人を知った日から6か月を経過すると告訴できなくなります。
(3)告訴の手順
告訴は、書面または口頭で行わなければなりません(刑事訴訟法241条1項)。
通常は、告訴状という書面を作成してこれを検察官または司法警察員に提出する方法で刑事告訴を行います。
なお、捜査機関では、刑事告訴をしようとする方に対して事前の相談を受け付けています。スムーズな刑事告訴を実現するためにも事前相談を活用するとよいでしょう。